
Eno.357 キョク とある塔の日々4 - めざめの平原

クローヴァル
「満を持して咲き誇った牡丹の花」
「満を持して咲き誇った牡丹の花」
大工も酒屋の弟子も惚れ惚れとした。
大輪の赤は炎のように深い奥行きを感じさせ、朝日の如く輝いて見えるほどだ。
これほど素晴らしい花を、しかも冬の最中に咲かせたのだ。
大工は、誰かに自慢したいという欲がふつふつと湧いて仕方がなくなった。
おもむろに酒蔵の外に出ると、風に乗って甘い香りが漂ってくる。
ようやく、庭の梅の木が黄色く咲き誇ったのだ。
ふもとには、それを満足げに眺める誰かが立っている。
大工が声をかけると、彼はこの辺りの木々を手入れする庭師だった。
黄色い梅、つまり蝋梅は、冬に咲く梅の中でも特に一足早く咲き誇る。
凍えるような風景に少しばかりの彩りを与えてくれる貴重な存在だと、庭師は胸を張った。
大工はここぞとばかりに対抗する。俺はこの寒風の季節に大輪の牡丹を咲かせた、と。
庭師は当然信じないが、その方が自慢のしがいがある。
大工はにやけ顔で、庭師を酒蔵へ連れ込むことにした。
扉の前で、大工は念を押すように言う。
「いいか、扉は体が通る隙間だけ開けるんだ。決して開け放してはならない。
あと絶対に、牡丹の前で『冬』だと口にしてはならない。今は『春』だということにしろ」
「どういうことだ?」
「いいから、いいから、絶対に守れ」
庭師は言われた通りに入り口に体を滑り込ませると、あっと声をあげた。
本当に、大輪の牡丹が咲き誇っている。
驚きのあまり閉め忘れそうになる扉を、大工が急いで閉じた。
庭師は開いた口が塞がらないまま、牡丹のまわりをぐるぐる、うろうろとした。
そんな庭師の姿を見て、牡丹が一言。
「蝋梅の香りがするな……?」
大工はぎくりとした。
庭師も思わず足踏みして。
「ああ……ええと……じ、沈丁花だよ。
先ほどまで庭で手入れをしていたが、香りが似ているかもしれないな?
今は春だから、もう蝋梅は咲いていないんだ」
見事の声の裏返りように、
牡丹は火が点いたかのように叫んだ。
「花を偽るとは何事か。
その格好は庭師か? 庭師の風上にも置けない奴!」
すると本当に、庭師の着物の裾に『火』が点いた。

ちょうちょ
「えっ」
「えっ」
庭師は悲鳴をあげて走り出し、酒蔵の戸を大きく開け放す。
大工が止める間もなく、寒風とともに淡い香りが吹き込んで、
灰色ばかりの景色の中心に、黄色く綻ぶ蝋梅が露わになった。
嘘つきめ、嘘つき、と恨めしい声が響いたが、大工は負けじと言い返す。
「最初に俺を騙したのはお前だろう!
『すぐ』に咲くと言ったのに咲かなかった!」
しかし、言い終わる前に大工の体が『発火』した。

ちょうちょ
「きゃーーーー!?」
「きゃーーーー!?」
のたうちまわる大工の体から火は絶えることなく、
酒樽や壁にまで燃え移り、酒蔵は火の海に包まれる。
火消しが集まっても、なかなか消し止めることはできない。
さらには島中が暖かくなり、皆、春が訪れたのかと錯覚した。
やがて大工も、牡丹も、酒蔵も燃え尽きた焼け跡には、
淡く香る蝋梅と、春の訪れに顔を出した草花のみが残っていたという……

ちょうちょ
「………………」
「………………」

クローヴァル
「……おい。大丈夫か」
「……おい。大丈夫か」

ちょうちょ
「へ、へいき……びっくりしちゃっただけなのよ!」
「へ、へいき……びっくりしちゃっただけなのよ!」

クローヴァル
「そうか。まあ、あと少しの辛抱だが」
「そうか。まあ、あと少しの辛抱だが」
さて、不思議なのは、この火事が燃え尽きた後も、島の気温が戻らなかったことだ。
それどころか、翌年も、その翌年も、秋が過ぎた頃になると急に気温が上がり、一足早い春が訪れるようになった。
この島は、冬を忘れてしまったのだ。
春柱島と名付けられたこの島はその後、春特有の賑わいと恩恵で栄えていくことになる。
酒蔵を丸ごと失った酒屋の弟子は干される羽目になったが、それを逆手に取った施策を打ち出し『春柱を生んだ酒屋』として観光の要となった。
また、裾に火をつけられ逃げ帰った庭師は、火事の供養として牡丹庭園を造り出した。
年明けには暖かな陽気の中、牡丹や春の花々が咲き誇る。
そして、島民たちは畏怖を示す。

クローヴァル
「百花の王とは、春の王。
閑散とした冬ではなく、百の彩りの中で偉大に咲いてこその王である。
ゆめゆめ、その顔に泥を塗ることなかれ」
「百花の王とは、春の王。
閑散とした冬ではなく、百の彩りの中で偉大に咲いてこその王である。
ゆめゆめ、その顔に泥を塗ることなかれ」
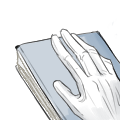
クローヴァル
「……おしまい」
「……おしまい」