
Eno.1 椋 京介 はなのきもち - はじまりの場所
花はそこに気高く咲き、
人はそれを見て何れを思う。
その花を見て希望を思うのは、
花を咲かせるが故に 水脈という「希望」を伝えたからか、
古き詩人がその花に「希望」の詩を乗せたからか。
その花は人から「希望」を与えられ、
その花は人へと「希望」を与える。
もっと言えば
花と人に限らず、砂漠の暑さ、水脈の清らかさ、詩人を育てた人やもの、装具の技術 etc...
そういった全てのものの関係性の中で、
"その花は希望を与えるもの"という、皆の中での"共通の幻想"を与えられた。
その花を見れば「希望」を感じる"べき"であり、
その花は人に「希望」を与える"べき"である。
そう思わされてしまうのではないか。
花はそこに気高く咲き、
人はそれを見て何れを思う。
そこには詩人も花言葉も水脈も熱砂もない。
そこには人と花のみ。人は花を、花は人を。
そうして人は初めて自由に思うことができるのだろう。
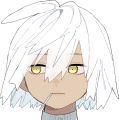
京介
「...アリス。」
「...アリス。」
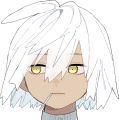
京介
「何を見て、何を感じて、何を思っているんだろうか。
僕の拙い土いじりでも咲く君は。」
「何を見て、何を感じて、何を思っているんだろうか。
僕の拙い土いじりでも咲く君は。」
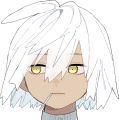
京介
「力強い宝石のような紫を湛えた君は、
きっと気高く、きっと自由な花なのかもしれない。」
「力強い宝石のような紫を湛えた君は、
きっと気高く、きっと自由な花なのかもしれない。」
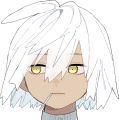
京介
「それはきっと、ただの願望に過ぎなくて、
それはきっと、ただそう思わされているだけなのかもしれないけど。」
「それはきっと、ただの願望に過ぎなくて、
それはきっと、ただそう思わされているだけなのかもしれないけど。」

京介
「それでも僕は........、君はそういう花だと思いたい。」
「それでも僕は........、君はそういう花だと思いたい。」
アリスはそこに気高く咲く。
僕はそれを見てアリスを思う。
Fno.2 アリス
「乾いた大地に、まるで空から降り立った旗のように咲く花がある。
紫に金を添えたその色は、遠くからでも風に揺れるのが分かるんだ」
そう語るのは、砂漠の街で行商をしている旅商人、サラームだ。
彼は旅の途中、荒野を越える際にアリスの花を見つけたという。
アリスは、すっと伸びた茎の先に紫の花弁を広げ、その中心に黄金の斑を抱く。
水をほとんど必要とせず、日差しの厳しい土地でも根を張るその姿は、砂塵に覆われた道行く者の目に鮮烈な印象を与える。
古い詩には、こんな話が残っている。
かつて、戦乱で故郷を追われた一人の少女が、果てのない荒野を越えねばならなかった。
彼女は何日も歩き、喉は渇き、足は砂に引きずられ、ついには立ち止まった。
そのとき、彼女の視界に紫と黄金の花が一輪、風に揺れていた。
少女はその花の根元に小さな泉を見つけ、命をつなぐことができたという。
やがて彼女はその土地に村を作り、アリスを守り神の花として祀った。
この逸話にちなみ、アリスには「希望」という花言葉が与えられた。
旅人の間では「道に迷ったとき、この花を見つけられれば帰り道が見つかる」という言い伝えもある。
「まあ、実際は花が道案内をしてくれるわけじゃないさ。
でも、足が前に出なくなったときに、この色を見れば……きっともう一歩、踏み出せるんだ」
サラームはそう言って、腰の革袋から乾燥させたアリスの花びらを一枚、風に乗せて放った。
花びらは夕陽に染まりながら、遠くへと舞っていった。