
Eno.1 椋 京介 はなのきもち - はじまりの場所
富士山には"御中道"と呼ばれるものがある。
富士山の五合目あたりにある道を指し、
富士信仰における修験道となっている。
御中道を御中道として成しているのは他でもない、生物によるものだ。
多くの植物は高い標高では根や葉を付けられず、
植物を食べる多くの昆虫や動物なども生きていくことはできない。
生と死の境界、それが御中道なのである。
境界を境界として成しているのは他でもない、変化によるものだ。
変化は得てして危険をもたらす。
が、誰かにとっての危険は誰かにとっての安寧でもある。
絶対的で普遍的な役名付けなど、できるはずもないのだから。
外敵を寄せ付けないが故の安寧か、
違いを認識することへの安寧か、
ひとたび境界線を超えれば立ちどころに死に至れる安寧か。
それはきっと、そこに根付くものにしか分からない。
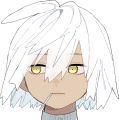
京介
「...フロス。」
「...フロス。」
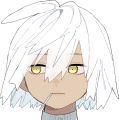
京介
「何を見て、何を感じて、何を思っているんだろうか。
境目に花咲く君は。」
「何を見て、何を感じて、何を思っているんだろうか。
境目に花咲く君は。」
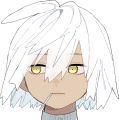
京介
「君はその境目で咲き、感じているのだろうか。
僕達と君達の違いを。」
「君はその境目で咲き、感じているのだろうか。
僕達と君達の違いを。」
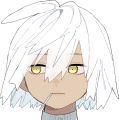
京介
「君は...そうして違いの中から、
人間の本質を見極めようとしているのだろうか。」
「君は...そうして違いの中から、
人間の本質を見極めようとしているのだろうか。」
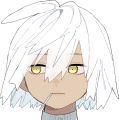
京介
「...僕はわからない。
それでも僕は...」
「...僕はわからない。
それでも僕は...」

京介
「僕のそれも本物であればいいと思うな。」
「僕のそれも本物であればいいと思うな。」
近年、地球温暖化によって御中道より上にも植物が育っているらしい。
他にも、重機に付着していた種子が落ちて芽生えた、などということも言われている。
境目はその時々で移り変ったり、無くなったりすることもある。
けれど、境目が無くなることは決してない。
全く同じ生き物など、この世には存在しないのだから。
Fno.11 フロス
「氷精は彼らの住処と、人里の境目で私たちを見守っているの。
だから、たまに林の縁には落とし物が落ちていて、それがフロスの花なんだって。」
ソラニワの一部地方で、その透き通る青紫の花は氷精の落としものとも呼ばれる。
園芸植物としては木漏れ日を好む特性から、例えばラバーの足元にグランドカバーとして植えるなど、背の高い植物の足元を彩るように使われることが多い。
また木漏れ日を好む特性から、野生のフロスは林の縁などに咲き、人の世界と精霊の世界を隔てる場所に咲くのだとも語られている。
そして逸話が示す通り、フロスは氷のような特性を持っている。熱を吸収し、”物を冷やす”という性質は、古くから冷却に使われてきた。
これはフロスが低温下で生育するために、周りの熱や光を多く吸収することでより低い温度に耐えるのだ。
”物を冷やす”歴史は、”火を扱う”歴史ほどは長くないが人はどの歴史でも冷やすことを探求しており、生活に同じぐらい重要なテーマであったと言えるのだろう。
「彼らは静かに見守っていて、私たちが落とし物を借りても許してくれているの。
だから、フロスを採りすぎて怒らせてはいけないよ。」
そうして子どもへ言い聞かせて、最後はこの言葉で締め括られる。