
Eno.1 椋 京介 はなのきもち - はじまりの場所
カラスは吉鳥をもたらすものだと言われる。
「日を呼ぶ鳥」と呼ばれ、数多の国で神聖視されている生き物である。
それは、太陽を背にすることでその身が黒いことによるものか、
人間とカラスが昼行性で親しみを持ちやすかったことによるものか、
カラスが人間と同じく賢く意志を持つように見えるからか。
兎角、カラスは信仰の対象として多くの人に信じられてきた生き物だ。
近年、カラスは凶兆もたらすものだと言われている。
カラスが鳴くと人死にが増えるとも言われている生き物である。
それは、その身が"穢れのように"黒いことによるものか、
人間とカラスが昼行性で、死肉やゴミを貪るところを見ることによるものか、
カラスが人間と同じくずる賢く意志を持つように見えるからか。
カラスはなにも変わっていなくとも、
世界が移り変ってゆく上で、そこから浮かび上がる意味はゆるやかに変わってしまうものだ。
それはきっと、誰にも止められないし、
それはきっと、誰が悪いわけでもない。
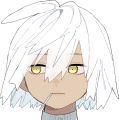
京介
「...ジネン。」
「...ジネン。」
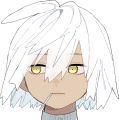
京介
「何を見て、何を感じて、何を思っているんだろうか。
火を呼ぶ花と呼ばれた君は。」
「何を見て、何を感じて、何を思っているんだろうか。
火を呼ぶ花と呼ばれた君は。」
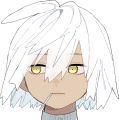
京介
「君は大変だったのだろうか。
火を耐えねばならなかったほどに。。」
「君は大変だったのだろうか。
火を耐えねばならなかったほどに。。」
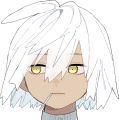
京介
「君は...火の中にしか生きる場所がなかったのだろうか、
それとも、火の中が居心地が良かったのだろうか。」
「君は...火の中にしか生きる場所がなかったのだろうか、
それとも、火の中が居心地が良かったのだろうか。」
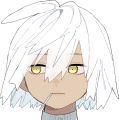
京介
「...僕はわからない。
それでも僕は...」
「...僕はわからない。
それでも僕は...」

京介
「君のその逞しさが、齧らずとも分かればいいな。」
「君のその逞しさが、齧らずとも分かればいいな。」
「火を呼ぶ花」は何を思い、何をもたらすか。
その赤の意味は、
その味の意味は、
火に強い意味は、
それでも尚花咲く意味は。
Fno.10 ジネン
地面が燃えている——ジネンを初めて見た者の多くは、そう錯覚する。
燃え立つような濃い赤の花弁は、鋭く尖り、陽光を受ければ本物の炎のように揺らめいて見える。その独特の姿が、ジネンという名の由来でもある。
花弁に含まれる色素は極めて耐熱性が高く、染料にすると色あせにくく鮮やかさが長く保たれる。また、花弁の辛味成分は舌を焼くような刺激を持ち、少量でも強烈な風味を加えるスパイスとして珍重されている。情熱の赤は人目を惹き、花壇ではまるでスポットライトのように他の花々を照らす役目も果たす。
ジネンはストロールグリーン島に庭園が造られる以前から存在し、島々の暮らしと深く関わってきた植物のひとつである。薬用や調味料、衣装の染め色として、生活の随所にその姿が見られた。だが、意外にも園芸植物として育てられるようになったのは比較的最近のことである。
かつてジネンは、「火を呼ぶ花」として恐れられていた。山火事の跡に、焦土の中でただひとつ赤々と咲き残る姿は、不気味とすら言われた。事実、火事の後にはジネンだけが焼け残っていたという目撃談が各地に残されている。
やがて庭園が築かれ、植物の調査と保護が進む中で、ジネンそのものに発火性がないことが判明する。それ以降、鑑賞や研究のための栽培が進められ、今日では園芸植物としても多くの花壇で育てられるようになった。
燃えるような見た目に反して、強く、静かに、どんな土地にも根を張るこの花は、暮らしの中に潜む「自然の力強さ」を静かに語りかけてくる。
その姿に心を動かされた者たちは、今もなお、ジネンを“燃えさしの花”と呼んで敬意を払うのだという。